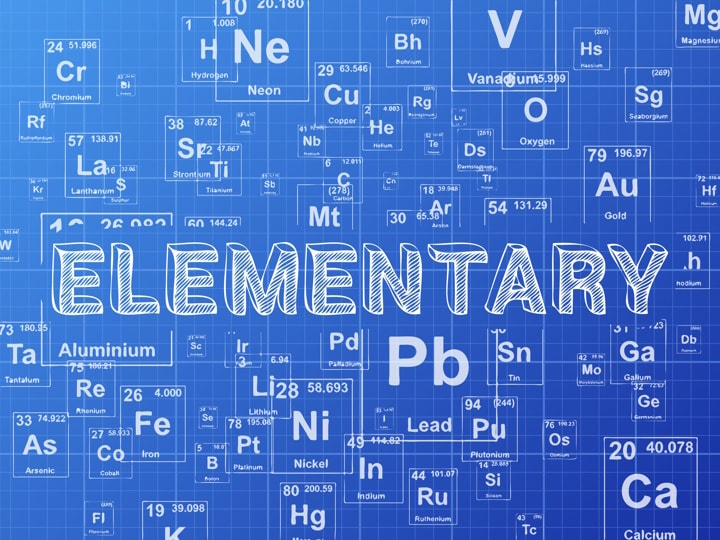有害金属
人々の健康や安全を守るため、食品および食品添加物に含まれる有害重金属の管理が求められています。日本国内では、『食品、添加物等の規格基準』や『食品添加物公定書』など、さまざまな法令が定められています。 溶液中の微量元素を高い精度で分析する代表的な装置としては、原子吸光分光光度計 (AA) やICP発光分析装置 (ICP-AES)、ICP質量分析計 (ICP-MS) があります。AAは特定の元素をシンプルな操作で高精度に分析することができます。ICP-AESは多元素の同時分析が可能であり、ICP-MSはICP-AESよりもさらに高感度な分析が可能です。また、ICP-MSはHPLCと組み合わせることで形態別ヒ素の分析も可能となります。一方、エネルギー分散型蛍光X線分析装置 (EDXRF) は固体試料や粉末試料を非破壊でそのまま分析することが可能であり、前処理不要で迅速な分析が可能です。

飲料水やその他の飲料中に含まれる有害金属は、消費者の健康を守るため、国内外で厳しく規制されています。
日本では、水道水の安全性を確保するため、水道法に基づき有害金属の基準値が定められています。清涼飲料水や粉末清涼飲料についても、食品衛生法に基づき有害金属の基準が設定されています。また海外においても、FDAやEFSAなどにより飲料中の有害金属の許容限度が設定されています。そのため、輸出入や国内流通においては、これらの基準を遵守することが求められます。

玄米中の有害金属に関する国内外の規制は、消費者の健康を守るために各国で設定されています。日本では、食品衛生法によりカドミウムに関する基準が設定されています。一方、香港や台湾、中国などでは、カドミウムに加え無機ヒ素や鉛について基準値が設定されています。これらの規制は、各国の食生活や環境状況、リスク評価に基づいて策定されており、輸出入や国内流通においては、これらの基準を遵守することが求められます。

粉ミルクや牛乳中の有害金属に関する規制は、消費者の健康を守るために国内外で厳格に規制されています。日本では、食品衛生法や関連する規格基準によって、製品中の有害金属の含有量や器具・容器からの溶出量が厳しく管理されています。国際的にも、コーデックス委員会や各国の規制当局が基準を設け、安全性の確保に努めています。

サプリメント中の有害金属に関する規制は、国や地域によって異なります。日本では、具体的な基準値が定められていないため、各企業が自主的に安全性を確保しています。一方、米国やEUでは、ガイダンスや評価に基づいて安全性の確保が図られています。

日本では、食品衛生法に基づき、魚介類中や食品、添加物中の有害金属の基準値が設定されています。国際的には、コーデックス委員会やFDA、EFSAなどが基準を設けています。