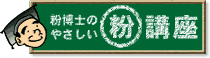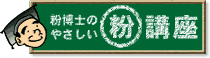| 「大きな石ころが河川の上流から下流、さらに海へと流れていく間に、だんだんと砕かれて小さな砂や土になる。」こんなお話を、むかし小学校で教わりました。
ところが、実際には「上流から下流にかけて大きな石から順番に川底に沈んでいき、小さな砂や土はなかなか沈まないので海まで流れ着く」ということのほうが正しいようです。つまり、川底にはどんどん土砂が溜まっていきます。そして、この土砂の溜まり方や溜まるポイントは土砂の粒度分布と密接な関係があるわけです。
|
|
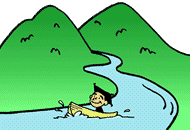 |
ダム湖に土砂が蓄積すると、貯水量が減少し、ダムとしての機能を果たすことができなくなってしまいます。また、河床に土砂が堆積した河川では、水害を防ぐためにより高い堤防を築かなければなりません。さらに、土砂が海洋に流出することによって、サンゴ礁や海洋生物に影響を及ぼしている事例も報告されています。
このような問題に総合的に対処するために、「水系一貫土砂管理」の必要性が叫ばれています。これは、河川の源流から河口・海岸に至るまでの「美しい水環境」、「豊かな水資源」、「安全な水域」を維持するために、水域全体を移動する土砂の量と質を的確に把握し、適切かつ総合的に管理しようという考え方です。
このためには、河川における土砂の生成や移動に関する詳細なデータが必要になるわけですが、まだまだ不明な点が多く、また季節や水量の影響も考慮すると、個々の河川の様々な観測ポイントで長期間にわたって粒度分布を測定する必要があります。
|