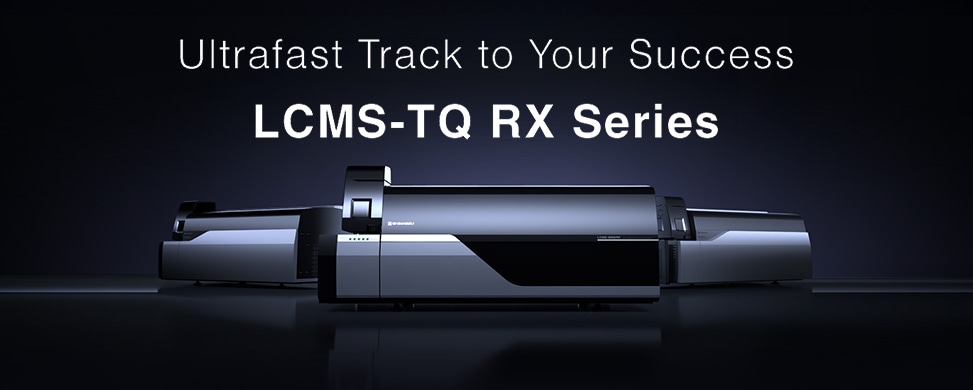
LCMS-TQ RX シリーズ
- LC-MS/MS法により、サキシトキシン(STX)、デカルバモイルサキシトキシン(dcSTX) 、ネオサキシトキシン(NEO)、デカルバモイルネオサキシトキシン(dcNEO)、ゴニオトキシン(GTX1~4)、プロトゴニオトキシン(C1~2)、デカルバモイルゴニオトキシン(dcGTX2、dcGTX3)の12分子種の一斉分析が可能です。 - シンプルなLCシステムを用いて、1分析15 minの高速分析が可能です。
貝毒は、主に二枚貝(ホタテガイ、アサリ、カキ等)が毒を持った海産渦鞭毛藻を捕食し、体内に毒が蓄積することで発生します。毒化した貝をヒトが食べると中毒症状を引き起こすことがあり、中毒症状により下痢性貝毒、麻痺性貝毒、神経性貝毒、記憶喪失性貝毒等に分類されます。 日本で問題となる貝毒は、主に麻痺性貝毒と下痢性貝毒であり、その毒素は複数の毒成分群により構成されます。日本では、食品衛生法に基づき貝毒に関する安全基準、規制値が設定されています(平成27年3月6日付け食安発0306第1号)。二枚貝等の可食部に含まれる毒力または毒量は、麻痺性貝毒で4マウスユニット/g 以下、下痢性貝毒で0.16mg オカダ酸当量/kg 以下と定められています。この麻痺性貝毒の規制値は、CODEXのCXS 292-2008、EC規則853/2004の基準値の 800 µg STX·2HCl equivalent/kg に相当します。現在の検査法は、麻痺性貝毒についてはマウス毒性試験法が、下痢性貝毒には平成27年3月6日付け食安基発0306第3号が通知されており、すでにLC-MS/MSを使用した機器分析法に移行しています。一方で、農林水産省は諸外国の状況を鑑み、麻痺性貝毒検査についても機器分析法の多機関妥当性評価を実施し、ガイドライン化事業を進めています。 国際的に麻痺性貝毒の検査法は、カナダ、米国の一部、ノルウェーなどで使用されている、The International ShipSecurity Certificate(ISSC)にて承認済みであるポストカラム酸化蛍光検出LC 法(J. AOAC Int. 2011, 94, 1154–1176)や、英国、アイルランド、ポルトガル、ニュージーランドなどが使用している2019年1月よりEUの公式参照法(OfficialReference Method)となったプレカラム酸化蛍光検出LC法(AOAC 2005.06)があります。ただし、これらのHPLCシステムはシステムおよび分析操作が煩雑であることから、近年は、親水性相互作用クロマトグラフィー(HILIC)を使用した超高速LC-MS/MS法も開発されています。2018年には21機関が参加し国際妥当性評価も実施され、LC-MS/MSを使用した機器分析法も、HPLC法と並んで有効とされています。本稿では、親水性相互作用クロマトグラフィーLC-MS/MS法で毒化したホタテ貝試料を分析した事例をご紹介します。
2022.03.03
一部の製品は新しいモデルにアップデートされている場合があります。